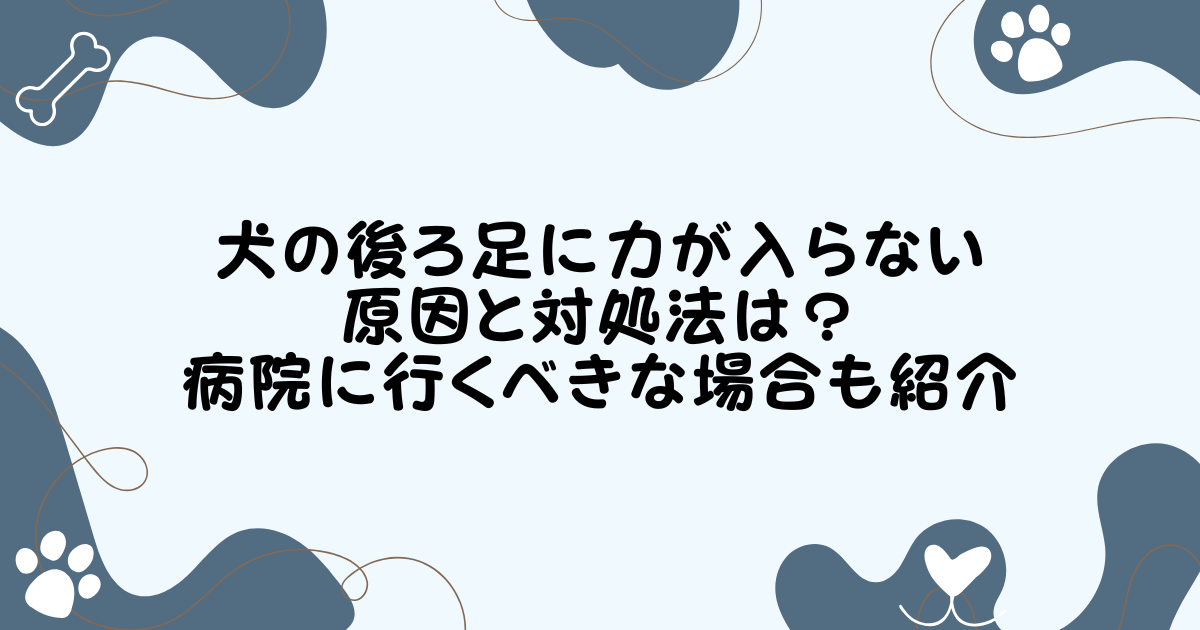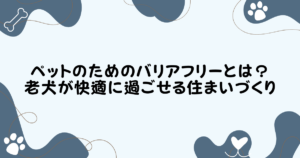愛犬の後ろ足に力が入らない、よろけるといった症状が見られたら、飼い主としては非常に心配になるものです。このような症状の原因には様々な可能性があり、早期発見・早期治療が大切です。
ここでは、犬の後ろ足に力が入らない原因と対処法について詳しく解説していきます。また、病院に行くべき症状と、飼い主にできるホームケアについても紹介します。
愛犬の健康を守るためにも、ぜひ参考にしてみてください。
犬の後ろ足に力が入らない原因とは?
犬の後ろ足に力が入らない原因は様々ですが、大きく分けると以下の4つが考えられます。
- ケガ
- 遺伝性疾患
- 神経系の異常
- 加齢
これらの原因による症状について詳しく紹介します。
ケガが原因の場合
犬が散歩中やドッグラン、室内で遊んでいるときに転んだりぶつけたりして、後ろ足を痛めてしまうことがあります。ケガの程度によっては、後ろ足に力が入らなくなったり、よろめいたりする症状が見られます。
ケガの場合、痛みのために後ろ足を庇うことがあるので、歩き方の変化に注意しましょう。また、ケガの部位を確認し、腫れや出血、変形などがないかチェックすることも大切です。
遺伝性疾患による後ろ足の異常
犬の中には、遺伝的に後ろ足に異常が出やすい犬種がいます。例えば、ミニチュア・ダックスフンドやウェルシュ・コーギーなどは、脊椎の異常により後ろ足に麻痺が出ることがあります。
遺伝性疾患による後ろ足の異常は、若い時期から症状が現れることが多いです。犬種特有の疾患については、ブリーダーや獣医師から情報を得ておくことが大切です。
神経系の異常が引き起こす後ろ足の問題
犬の脳や脊髄に異常が起こると、後ろ足の動きを司る神経に影響が出ることがあります。これにより、後ろ足に力が入らなくなったり、よろける症状が現れたりします。
神経系の異常は、外見からは判断しづらい場合があります。後ろ足の症状だけでなく、痛みやしびれ、排泄の問題など、他の症状にも注意が必要です。
加齢に伴う後ろ足の筋力低下
犬も年齢とともに筋力が低下していきます。特に後ろ足は体重を支える重要な役割を担っているため、加齢による筋力低下の影響を受けやすく、力が入らなくなったりふらついたりすることがあります。
シニア犬の場合、加齢に伴う筋力低下は避けられません。しかし、適度な運動や体重管理、バランスの取れた食事などで、筋力低下のスピードを遅らせることができます。
また、足腰の弱った犬でも安心して過ごせるように、家の中の環境を整えることも大切です。滑りにくいフロアマットを敷いたり、段差を減らしたりするなどの工夫が有効です。
バリアフリー対策の具体的なやり方に関しては、こちらの記事で詳しく解説しています。
後ろ足に力が入らない・よろける症状を引き起こす主な病気
後ろ足に力が入らない、よろける症状の原因となる病気には、突発的に症状が現れるものと、徐々に進行するものがあります。それぞれの特徴を理解し、適切な対応を取ることが大切です。
突発的に症状が現れる疾患
突発的に後ろ足の症状が現れる疾患としては、以下のようなものがあります。
脊椎・脊髄疾患
椎間板ヘルニアやウォブラー症候群など、脊椎や脊髄に異常が起こると、後ろ足に麻痺が出たり、力が入らなくなったりします。
脊椎・脊髄疾患は、動きが急に変化したり、痛みを感じたりすることで発症することがあります。後ろ足に力が入らない、歩き方がおかしいといった症状が見られたら、速やかに獣医師の診察を受けましょう。早期の治療開始が回復のカギとなります。
脳疾患
脳腫瘍や脳炎など、脳に異常が起こると、後ろ足の動きに影響が出ることがあります。
脳疾患の症状は、後ろ足の異常だけでなく、けいれんや意識障害、視覚障害など多岐にわたります。これらの症状が見られた場合は、すぐに獣医師に相談しましょう。脳疾患の治療には専門的な知識と設備が必要となるため、早期の受診が重要です。
整形外科疾患
骨折や靭帯断裂など、後ろ足の骨や関節に異常が起こると、痛みによって後ろ足に力が入らなくなります。
外傷が原因の整形外科疾患では、事故やケガの直後から症状が現れます。後ろ足を痛がって動かさない、触ると嫌がるなどの症状があれば、獣医師の診察が必要です。レントゲン検査などで的確に診断し、適切な治療を行うことが大切です。
徐々に進行する疾患
徐々に症状が進行する疾患としては、以下のようなものがあります。
進行性の脊椎・脊髄疾患
変性性脊髄症などの進行性の疾患では、徐々に後ろ足の麻痺が進んでいきます。
初期段階では、後ろ足の動きがぎこちなくなる程度ですが、次第に麻痺が強くなり、歩行が困難になっていきます。進行性の疾患では、早期発見と継続的な治療が重要です。獣医師と相談しながら、適切な療法を行っていく必要があります。
ゆっくり進行する脳疾患
脳腫瘍などの脳疾患の中には、ゆっくりと症状が進行するものもあります。
初めは後ろ足の動きがおかしいといった程度ですが、徐々に歩行障害が悪化していきます。脳疾患は早期発見が難しいため、高齢犬では定期的な健康診断が大切です。異常が見つかった場合は、MRIや CT検査などで詳しく調べる必要があります。
変形性関節症などの整形外科疾患
加齢に伴って関節の変形が進むと、徐々に後ろ足に力が入らなくなっていきます。
変形性関節症は、関節の軟骨が磨耗し、炎症や痛みを引き起こす病気です。初期は運動後の痛みから始まり、徐々に常時痛むようになっていきます。体重管理や適度な運動、サプリメントの使用など、獣医師と相談しながら適切なケアを行うことが大切です。
後ろ足の異常が現れやすい犬種の特徴
後ろ足の異常は、犬種によって発症しやすい傾向があります。代表的な犬種と、関連する疾患は以下の通りです。
| 犬種 | 関連する主な疾患 |
|---|---|
| ミニチュア・ダックスフンド | 椎間板ヘルニア、半側椎骨、変性性脊髄症 |
| ウェルシュ・コーギー | 変性性脊髄症 |
| フレンチ・ブルドッグ、パグ | 半側椎骨 |
| ドーベルマン | ウォブラー症候群 |
これらの犬種を飼っている場合は、後ろ足の異常について知識を深め、予防と早期発見に努めることが大切です。定期健診では、後ろ足の症状だけでなく、関連する疾患の兆候がないかもチェックしてもらいましょう。
病院に行くべき症状と行く必要がない症状
犬の後ろ足に異常が見られた場合、どのような症状の時に病院に行くべきなのでしょうか。また、様子を見ても大丈夫な症状にはどのようなものがあるのでしょうか。
病院に行くべきな場合
以下のような症状が見られる場合は、速やかに獣医師の診察を受けましょう。
- 後ろ足が完全に動かない、まったく体重をかけられない
- 明らかな外傷(骨折、脱臼など)がある
- 激しい痛みを感じているようで、鳴いたりぐったりしたりしている
- 排尿や排便ができない、またはコントロールできない
- 意識がない、けいれんを起こしている
これらの症状は、重篤な疾患を示唆している可能性があります。早期の治療開始が回復の鍵となるため、症状を見つけたらすぐに獣医師に相談することが大切です。
病院に行く必要がない場合
一方で、以下のような症状であれば、すぐに病院に行く必要はないかもしれません。
- 足をぶつけたりしたが、腫れや痛みが軽度で歩行に大きな支障がない
- 疲れているだけで、休ませると元気になる
- 加齢に伴う足腰の衰えで、ゆっくりとした動作になる
ただし、これらの症状でも、数日経っても改善が見られない場合は、獣医師に相談しましょう。症状が軽度であっても、重篤な疾患が隠れている可能性があるためです。また、シニア犬の場合は、少しの異変も見逃さないようにすることが大切です。
後ろ足に異常が見られた時の対処法とNG行動
愛犬の後ろ足に異常が見られた時、飼い主にできる対処法と避けるべき行動について説明します。
愛犬をケージで安静にする
後ろ足に何らかの異常が見られた場合、まずは安静にすることが大切です。動き回ることで症状が悪化したり、ケガの部位を痛めたりしてしまう恐れがあるためです。
ケージなどで愛犬を静かに休ませ、様子を見ましょう。この際、トイレ、食事、水飲みの場所を工夫し、なるべく動かなくて済むようにすることが大切です。安静にすることで、症状が改善する場合もあります。
避けるべき対処法
愛犬の後ろ足に異常が見られた時、以下のような対処は避けましょう。
- 痛みを我慢させて、無理に歩かせる
- 自己判断で痛み止めなどの薬を与える
- 病院に行かずに様子を見続ける
痛みを我慢させることは、愛犬にとって大きなストレスとなります。また、無理に歩かせることで、症状を悪化させてしまう恐れもあります。
獣医師に相談せずに、自己判断で薬を与えることも危険です。症状を一時的に和らげるだけで、根本的な治療にはならないことがあるためです。
異常が見られたら、早めに獣医師に相談し、適切な治療を行うことが大切です。飼い主の判断で様子を見続けることは、愛犬の命に関わる危険性もあることを認識しておきましょう。
まとめ:後ろ足の異常は早期発見・早期治療が肝心
犬の後ろ足に力が入らない、よろける症状は、様々な原因が考えられます。ケガや遺伝性疾患、神経系の異常、加齢による筋力低下など、その原因を突き止め、適切な治療を行うことが大切です。
症状が見られたら、愛犬をケージで安静にし、速やかに獣医師に相談しましょう。重篤な疾患が隠れている可能性もあるため、飼い主の判断で様子を見るのは避けましょう。
また、日頃から愛犬の歩き方や姿勢に注意を払い、異変を早期に発見することも重要です。定期的な健康診断で、後ろ足の状態をチェックしてもらうことも有効な予防法の一つです。
愛犬の健やかな暮らしのために、飼い主ができることは少なくありません。後ろ足の異常は、早期発見・早期治療が何より大切です。愛犬のささいな変化も見逃さず、適切な対応を心がけましょう。